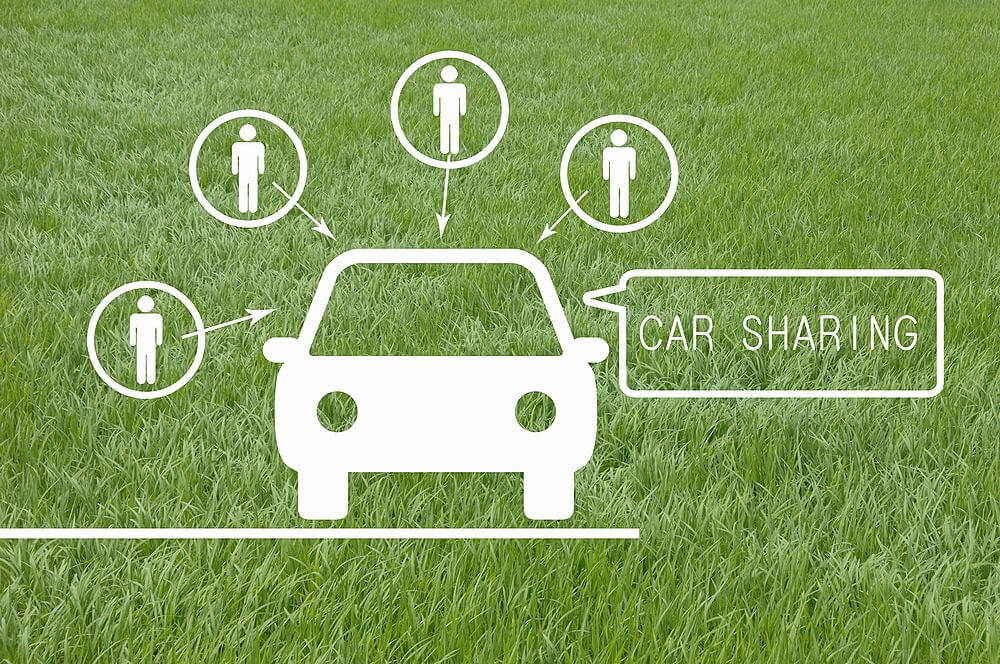当記事は「わかるWeb」メールマガジンの過去記事です。メールマガジンの登録はこちらです!
その日、男は、渋谷発成城学園前行きのバスに乗っていた。
「仕事を辞めさせてください。もう無理です」
それを言うために、仕事場に向かっている。
彼の仕事は、ぬいぐるみ(着ぐるみ)を着て、カメラの前で演技をするものだ。
ただし、それは壮絶なものだった。
体にぴったりのゴム製のぬいぐるみとマスクを着るため、前がよく見えず、呼吸困難になり、1回に15分続けるのが限界だった。
ぬいぐるみに火が燃え移りそうになったり、マスクに水が入って息ができなくなったりと、何度も、命の危険にさらされた。
何ヶ月もの間耐えてきたが、心身ともに限界に来ていた。
始めたころから、体重が5kg以上減った。
「自分には、もうこの仕事は無理だ。辞めさせてもらおう」
それを告げに行くために、バスに揺られていた。
途中で、小学生たちが乗ってきた。
彼らは口々に言った。
「ウルトラマンが怪獣をやっつける時の、スペシウム光線がかっこいい!」
「昨日の怪獣は強かったな!ウルトラマンが負けそうになったね」
「ウルトラマンは、どうして3分間しか地球にいられないのかな?」
「次の回が、早く観たいな!!」
目を輝かせて、夢中に話している。
少年たちの言葉に、男は衝撃を受けた。
なぜなら、男が演じていたのは、ウルトラマンだったのだ。
今回は、以前掲載した、1966年ごろの「初代ウルトラマン」のお話の続編です。
(ウルトラマンのお手本はウルトラマン自身?)
「男」とは、初代ウルトラマンのスーツアクター(ぬいぐるみ役者)である、古谷敏(ふるやさとし)さんです。
この投稿をInstagramで見る
宇宙の彼方から地球にやってきた宇宙人(ウルトラマン)。
この、前例のない役柄を演じた、当時22歳の古谷さん。
その撮影現場は、壮絶なものでした。
東宝演劇学校を卒業し、東宝のニューフェイスとして、いくつかの端役でエキストラ出演しました。
しかし、数年経っても俳優としてなかなか芽が出ません。
そこに、スーツアクターとしての仕事が舞い込んできたのです。
それが「ウルトラマン」です。
(ここでは、「ウルトラマン」とは全て第一作の初代ウルトラマンのことを指します)
役者は顔を売るのが商売なのに、スーツアクターでは顔が出ない。
それに、以前何度かぬいぐるみを着て宇宙人や怪人の役をやったことがあって、その大変さ・辛さも知っている。
だから、古谷さんは断りました。
「自分は、たとえチョイ役でもいいから、顔が出る俳優としてやっていきたい」
そう伝えました。
しかし1966年ごろの当時、それまで隆盛だった映画が衰退し、テレビ業界が伸びてきて、「ドラマ」も映画館ではなくてテレビで盛んに放映されるようになってきていました。
このご時勢、映画俳優を目指しても、全く芽が出ないままで終わってしまうかもしれない。
いやそれ以前に、仕事がなくて食べていけないかもしれない。
そんな不安が、同時にあったことも事実です。
この投稿をInstagramで見る
古谷さんがウルトラマンの役をやることになった一番の理由は、青森のデザイナーであり彫刻家である成田亨(なりたとおる)さんの情熱でした。
成田さんは、ウルトラマンはもちろん、作品に出演する怪獣、宇宙人、科学特捜隊の隊員のユニフォーム、さらには科学特捜隊の飛行機(ビートル機)などに至るまで、ほぼ全てのデザインを担当しました。
つまり、ウルトラマンは、視覚的には「成田亨の世界」だったのです。
その成田さんが、「今デザインしているウルトラマンは、どうしてもビンさん(古谷さんの愛称)に演じてもらいたい」、と古谷さん本人に熱烈に迫ったのです。
「(以前宇宙人のスーツアクターをやったときの)ビンさんの長身、細身の体、頭の小ささ、手足の長さ、そして演技にいたるまで、ウルトラマンは、全てビンさんをイメージしてデザインしたんだ」
「他の隊員役は、誰にでもできる。
でも、ウルトラマンは、ビンさんでないとできない。
この映画は、誰がなんと言おうと、ウルトラマンが主役なんだよ」
(当時テレビドラマも、小型の「映画」という感覚だったのかもしれません。「映画」と呼んでいたようです)
成城学園前の本格的な中華料理屋で、古谷さんは成田さんに丁寧に説得され、その後いろんな人の意見も聞き、やがて、ウルトラマンのスーツアクターをやる決心をしました。
View this post on Instagram
それにしても、ぬいぐるみ(着ぐるみ)の役で、ここまでこだわった作り方をすることなど、現在のテレビ番組ではあるんでしょうか?
当時のウルトラマンのスタッフは、美術の成田さんや監督の実相寺昭雄さんを初め、優れた人たちが揃っていました。
20代が多かったそうですが、誰もが自分の仕事に責任を持ち、出演者や他のスタッフを気遣い、常に良いものを作ろうと一丸になっていたようです。
撮影がどんなに遅くなっても、たとえ徹夜になっても、みんな手を抜かずに仕事を続けていたと、古谷さんは証言しています。
撮影が深夜になると、忙しいスタッフに比べて、逆に手が空いた監督が、スタッフ・出演者のために、自らインスタントラーメンを作って振舞っていたことが、しばしばあったようです。
そのために、スタジオの片隅には、常にインスタントラーメンが常備されていたとのことです。
それから数ヶ月間、古谷さんの驚くべき戦いは続きます。
まず、ぬいぐるみは一人では着脱できない。
数人がかりでマスクとスーツを付け、その境目にテープを貼り、さらに上から銀の塗装をする(ウルトラマンは銀と赤のデザインです)。
スーツをつけると、全身が締め付けられて手足がしびれてくる。
マスクに開けた、ごく小さな穴から外を見るが、よく見えない。
監督の声も、マスクを通して小さくしか聞こえない。
呼吸しづらくて、頭がボーっとしてくる。
体にピッタリのゴムのスーツやマスクは、ライトが当たっただけで、触れられないほど熱くなる。
冷や汗なのか熱いからの汗なのか、汗が滝のように流れる。
この状態で、吊るされた棒に捕まって飛び降りたり、ゴロゴロ転がったり、怪獣に飛びかかったりする。
常に体中に打撲ができて、ひどいときには内出血したり、とにかく体を酷使する、そして命の危険もある。
まさに、修羅場のような状況でした。
冒頭の通り、迫力のあるシーンを撮るために火や水を使い、ガソリンや火薬も使いました。
爆発で、爆風や土、砂利が飛んでくる。
海の模型のシーンで実際に水に入って演技すると、小さな覗き穴から水が入り込んでマスクの中で溜まり、息ができなくなる。
その恐怖。
この投稿をInstagramで見る
撮影中に、スーツの中で気分が悪くなってきて、マスクをはずして吐いてしまう。
食べて撮影に臨むと吐いてしまうので、食べずに水と牛乳しか入れていないのに、それでも吐いてしまう。
しかし、古谷さんは、みんなに見られないように、いつもスタジオの隅に行って吐いていたそうです。
それは、芸能学校のころ「俳優は、どんなときでもカッコよくしていなければならない」と教えられたからです。
実直な人だったのですね。
撮影中、どうにも苦しくて耐えられなくなったとき、手でバツを示して撮影を中断してもらう。
すると、待機していたスタッフが、すぐにマスクとスーツを脱がしてくれる。
こんな調子で、続けて演技するのは15分ぐらいが限界だったそうです。
通常の演技どころか、簡単な動きをするのにも大変な思いをしていました。
自分は、本当にこの仕事を続けられるのだろうか?
常にそんな思いにかられて、悩んでいたそうです。
それでも古谷さんは、一生懸命にトレーニングや役作りをしていました。
体型が変わったらぬいぐるみが着れなくなるわけですから、腹筋・背筋を毎日300回やる。
ウルトラマンの得意技である「スペシウム光線」の構えを毎日300回(!)行い、どうやったら手がマスクにかぶらずによく映るのか、どうやったらカッコよくできるのか、自分なりに血のにじむような練習しました。
スペシウム光線とは、ウルトラマンの必殺技で、よく見る「手を十字に組んで光線を出すポーズ」です。
また、独特の「ウルトラマンが猫背になって構えるポーズ」は、古谷さんが好きだったジェームス・ディーンがナイフを構えるポーズをイメージして、自分で研究したそうです。
View this post on Instagram
こうして一生懸命演じるてはいるものの、古谷さんの悩みはよりいっそう深くなっていきました。
たまに、別なスタジオで撮影している「隊員役の人たち」を見ると、和気あいあいと演技していて楽しそうです。
「自分もこの一員になれたらなあ。顔を出して演技できたらなあ」と羨んでいました。
連日の過酷な撮影で、撮影開始時に60kg以上あった体重が55kgに減ってしまった。
スタッフは、とてもよくケアしてくれるけど、でも本当の大変さや恐怖は、自分にしかわからない。誰にも理解することはできない。
そう思っていました。
とても疲弊して孤独な状態だったのでしょう。
そして決定的だったのは、当時のある新聞記事を見たときでした。
「空想特撮テレビ映画とはほど遠い「ウルトラマン」」
「怪獣と宇宙人がただプロレスごっこをしているだけで、見るに堪えない。子供だましだ」
厳しい評価です。
古谷さんは思いました。
「僕だって、かっこいいウルトラマンにしたいんだ!
でも、ぬいぐるみの中の苦しさは誰にもわからない!
僕にしかわからないんだよ!」
もはや、古谷さんの心境は出口なしの状態です。
体力的にも精神的にも、にっちもさっちも行かなりました。
そして古谷さんは、仕事場である世田谷区砧(きぬた)の円谷プロダクションに、役を降りることを告げに行ったのです。
この投稿をInstagramで見る
そして、冒頭のシーンです。
バスに乗り合わせてきた少年たちが、夢中になってウルトラマンのことを話しています。
目を輝かせて、本当に楽しそうに、興奮した様子です。
みんながみんな勝手にしゃべるので、ただただにぎやかです。
古谷さんは、子供たちの言葉に衝撃を受けます。
本当なのか?
自分がやっているウルトラマンは、こんなにもすごいのか?
子供たちは、次回が待ち遠しいと言っている。
毎日必死に練習してきたスペシウム光線が、カッコいいと言っている。
こんなにも喜んでいる。
こういう子供たちが、全国にいるのか?
だから、ウルトラマンは視聴率が高いのか。
数え切れない子供たちが、ブラウン管に釘付けになってウルトラマンを見ているんだ!
そのとき、古谷さんは思ったそうです。
子供たちは、ウルトラマンをヒーローだと思っている。
そんな子供たちのことを、自分は全く見ていなかった。
自分のことで精一杯で、辛いだの、苦しいだの、怖いだの、修羅場だのと、思い悩んでいた自分が恥ずかしい。
自分ばかりが大変なのではない。
脚本家も、監督も、デザイナーも、スタッフも、出演者も、怪獣のスーツアクターも、みんなが頑張って作っているのが「映画」なんだ。
「自分の辛さはわかってもらえない」など、とんだ思い上がりだったんだ。
みんなに申し訳ない。
古谷さんは、バスの中で気持ちを入れ替えました。
そして「子供たちが夢を育てる手伝いをしよう」そう思ったそうです。
そのとき、ウルトラマンは子供たちに助けられた。
古谷さんはそう思いました
バスを降りたら、そのバスを見送りながら、子供たちに「ありがとう」と頭を下げました。
そして、降板を告げるのではなく、いつもより元気に仕事場に入って行ったのです。
この投稿をInstagramで見る
それからも、大変な撮影は続きましたが、彼の気持ちは変わっていきました。
スーツアクターである彼が、監督に演技プランを提案したり、それによって脚本を変えてもらったり、精一杯「自分のウルトラマン」を演じたのです。
過酷な仕事であっても、活気のある楽しい気持ちで取り組んだのです。
その後、ウルトラマンの動きは、周りのスタッフが見てもわかるほど、良くなっていったそうです。
やがて古谷さんは、「ウルトラマンの役は誰にも渡せない!最後まで自分がやりきるんだ!」そう思うに至ったそうです。
古谷さんの姿を見ていた関係者やファンからの要望で、古谷さんは「ウルトラマン」の次に制作された「ウルトラセブン」で、アマギ隊員という役で出演することになりました。
ついに、スーツアクターではなく、顔を出して演じる俳優としてレギュラー番組が決まったのです。
ウルトラマンで古谷さんがやってきたのは、誰が見ても尋常ではない大変な仕事です。
どんなに悩んでも、落ち込んだとしても、無理もないことだと思います。
でも、当人の気持ちひとつで、その過酷な状況も、やりがいのある、価値のある、もっと続けていたい仕事に変貌したのでしょう。
私たちも、辛いとき、苦しいとき、弱音を吐くし、愚痴も言います。
しかし、仕事や生活の中で、とらえ方ひとつで、自分にとってかけがえのない価値を見つけることができるのかもしれません。
古谷敏さんはこうして、苦しみと悩みを突き抜けて、ウルトラマンになったのです。
(古谷さんの体験記は「ウルトラマンになった男(小学館)」から抜粋・引用 メルマガ用に調整しています)
この投稿をInstagramで見る
この投稿をInstagramで見る